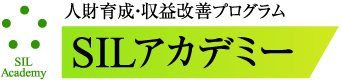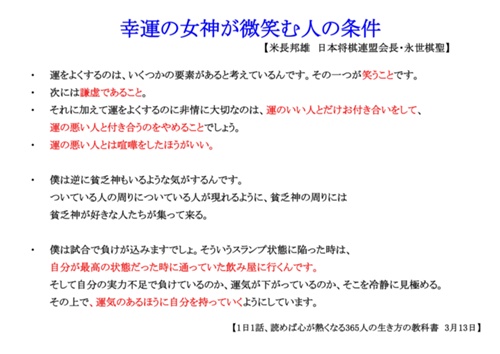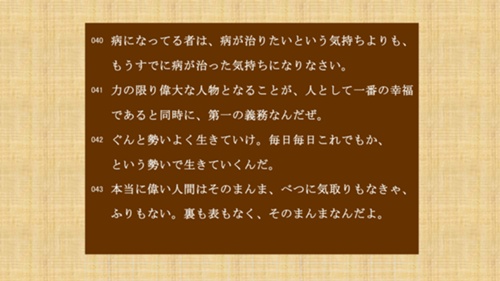【アモリ通信546】 年金倍増
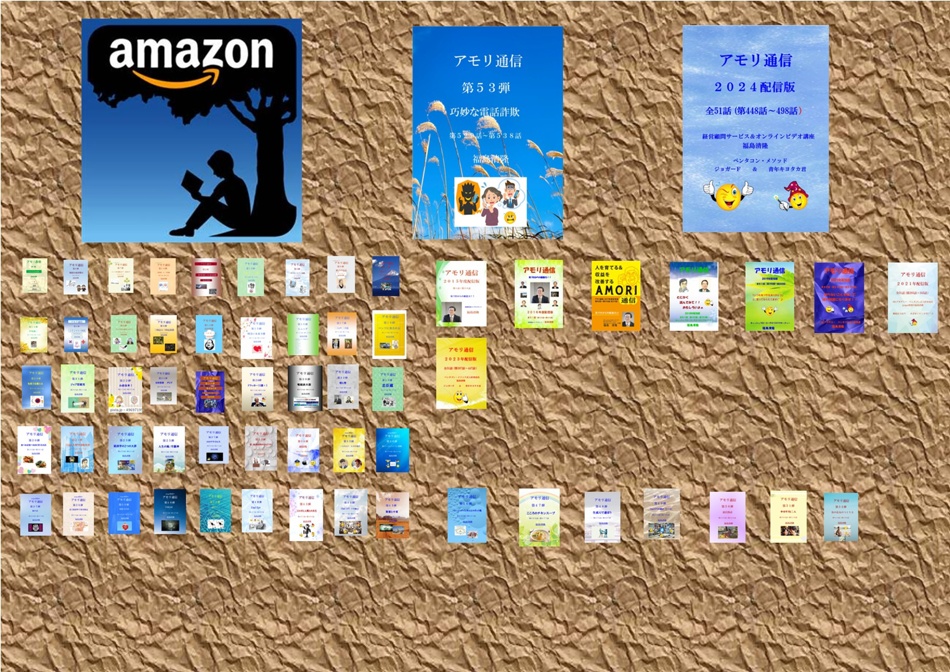
◎◎さん(^^♪
こんにちは。
数字と人を育てる経営を、あなたの会社に。
「数字と心」が経営の両輪です。
ペンタゴン・メソッド
本日のテーマは
『年金倍増』です。
【年金倍増】で日本経済は大復活する!
デフレの終わり、第二の「高度成長」の始まり
三橋孝明 経営科学出版
(私見 1)
2週続けて三橋孝明氏の書籍です。
取り上げるんだからコイツは三橋孝明のファン
なんだな、と・・世の中、そんなものですね。
反論するのが面倒なのでスルーします(💦)
それよりも、いつも生成AIに質問して、
その質問文と回答をまともに転写しています。
それと、生成AIにも間違いがあるという
「当り前」に気づくことが最近ありました。
「ChatGPT(有料版)一筋」にもそれなりの
リスクがあることを体験しました。
その具体的な内容の説明は回避します。
今回はgeminiの無料版に質問し、あたかも
自分で書籍を読んでまとめたように記載して
みました。
主要な論点
-
デフレ脱却と経済成長の鍵は「年金倍増」
この書籍の最も中心的な主張は、デフレの
原因が「需要不足」であり、これを解決する
ためには「消費を増やすこと」が不可欠だと
いう点です。
そして、その具体的な手段として、年金給付
額を大幅に引き上げ、高齢者の消費を促すこ
とで、経済全体に活力を与え、デフレから脱
却できると論じています。
-
積極的な財政出動の必要性
著者は、日本の経済停滞の背景に、緊縮財政
があると考えている。年金倍増は、その財源
を国債発行などの積極的な財政出動によって
賄うべきだと主張しており、財政規律よりも
経済成長を優先するべきだという考えを示し
ています。
-
第二の「高度成長」の可能性
年金倍増による消費の活性化が、最終的には
企業収益の改善、賃金上昇、設備投資の増加
といった好循環を生み出し、かつての高度経
済成長期のような力強い経済成長が再び可能
になると述べています。
これは、単なる経済回復ではなく、新たな成
長フェーズへの移行を目指すものです。
これらの要点は、著者が長年主張している
「反緊縮」「積極財政」の考え方を、「年金
」という具体的な政策に落とし込んだものと
解釈できます。
第二の「高度成長」の可能性についてもっと
詳しく記載します。
第二の「高度成長」のメカニズム
著者が提唱する「第二の高度成長」のシナ
リオは、以下の好循環によって成り立ってい
ます。
1.年金倍増による需要創出:
まず、政府が国債発行などで財源を確保し、
年金給付額を大幅に引き上げる。
これにより、高齢者層の手元に現金が増え、
消費意欲が高まる。
2.企業の収益改善:
高齢者の消費が増えることで、小売業やサ
ービス業など、内需に依存する企業の売上が
増加する。これにより、企業の収益が改善す
る。
3.賃金上昇と設備投資:
収益が改善した企業は、従業員の賃金を引
き上げたり、生産能力を増強するための設備
投資を行ったりする。
4.若者層の消費拡大:
賃金が上がった現役世代も、将来への不安
が減り、消費を増やす。
これにより、経済全体でさらに需要が拡大
する。
5.税収増と財政健全化:
経済が成長し、企業の利益や個人の所得が
増加することで、国や地方の税収が増える。
結果として、国債発行で膨らんだ財政赤字を
徐々に解消できる、という好循環が生まれる。
この一連の流れは、「需要不足」という根本的
な問題を解決し、かつての高度成長期にみられ
たような、経済が自律的に拡大していくサイク
ルを再現できるという考えに基づいている。
なぜ「高度成長」なのか
この考え方が単なる景気回復ではなく「高度
成長」と表現される理由は、以下の点にあり
ます。
•継続的な好循環:
年金倍増という一時的な 景気刺激策に留ま
らず、それが経済の構造そのものを変え、
需要と供給が継続的に拡大する「構造的な
成長」を目指しているからである。
•民間投資の活発化:
消費が増えれば、企業は将来の需要を見込ん
で積極的に投資を行うようになる。この民間
投資こそが、経済を長期的に成長させる原動
力だと考えられている。
•デフレからの完全脱却:
賃金と物価がともに上昇する健全なインフレ
状態となり、デフレの根深い問題から完全に
脱却できると主張している。
著者のこの主張は、緊縮財政を優先する多く
の経済学者や政策立案者とは一線を画してお
り、その是非については様々な議論がある。
しかし、著者の論理は、日本経済の最大の課
題を「需要の創出」に置き、大胆な政策でこ
れを解決しようとするものである。
(私見 2)
生成AIに分析させて、その回答をあたかも
自分が調べたように編集して「完成」させる
のは今では多くのビジネスパーソン他にとっ
て「当り前」の事なのかもしれません。
然しながら「生成AIにも間違いがある」と
いうことを肝に銘じておく必要があります。
ただ、誰かの書籍の要点をまとめるという
「作業」なら異なる生成AIによる違いは少な
いかもしれません。
いずれにせよ、「自分で読んでまとめる」
という「地道な努力」は大切でしょうが、
『時代は変わったのだ。いろいろな生成AI
に分析させて、その分析結果で、どれがより
正しいか。しっかり判断するのが人間の役割
だ』のような考え方に私はなっています。
私の場合・・・自分がまとめるより、
生成AIがまとめたものが(残念ながら?)
確実に無駄がなく分かり易いものになってい
るように思います。読み手はそちらの方が
いいに決まっています(💦)
【追記】
私は財務省主導の「緊縮財政」よりも、一部
の経済学者・評論家・政治家が主張している
「積極財政」派です。
著者も積極財政派です。この原稿を仕込んで
るのは、自民党総裁選がスタートした時期です。
どうもマスコミの基本姿勢は「緊縮財政」派
の人物を持ちあげる方向性があるように思えて
なりません。マスコミ(も)、財務省の影響下
にあるそうなので、やむを得ないのかも知れま
せんが。しかし・・・・・日本の将来の為には
、何が正解か。政治家も自分の生残りばかりで
はなく、本来の役目を果たしてほしいと思うの
ですが・・・・・
【追記2】
先週も【追記】で述べましたが、高市政権が
発足しました。積極財政推進の政権がスタート
しました。財務省や自民党内の一部や野党の
一部から猛烈な反発を既に受けているよう思わ
れます。「日本復活」の為に、高市さん、高市
政権に頑張ってほしいと私は願っています。
◎◎さんは、上記の私の考え方を
どのように思われるでしょうか?
ご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
◎◎さんの幸運な日々を祈念します。
【SILアカデミー ペンタゴン・メソッド】
https://www.sil-ms.jp
【50秒動画 SLBテンプレート&ペンタゴン・メソッド】
https://www.sil-ms.jp/173749.html
【SLBテンプレート 23】
https://note.com/sil5853/n/n269d790417d6